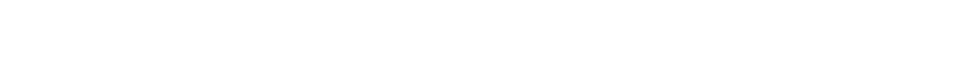INTERVIEW
05
三宅 香帆 さん
文芸評論家 / 京都市立芸術大学非常勤講師
本棚は単なる収納ではなく、
日常に古典の視点を取り入れ、思考の幅を広げる存在。

三宅 香帆 Kaho Miyake
文芸評論家、京都市立芸術大学非常勤講師。1994年高知県生まれ。リクルート勤務後独立。著書に『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』『「好き」を言語化する技術』など。
千年前の言葉と暮らす─本棚から広がる時間旅行
大学時代の恩師の言葉をきっかけに、本棚を「知識を拡張する装置」として捉えるようになった三宅香帆さん。本棚は単なる収納ではなく、日常に古典の視点を取り入れ、思考の幅を広げる存在だという。小さい頃からの読書習慣や古典文学への関心、本棚との出会いと活用法についてじっくり語っていただいた。

本棚との出会い
──当社の本棚を知ったきっかけを教えてください
もともと夫が知っていて、最初に購入したのも夫なんです。たしかインターネットの記事やSNSで、誰かがこの本棚を使っているのを見たと話していました。写真を見て「これだ」と思ったそうです。
──最初に使っていたのはご主人だったんですね。
はい。一人暮らしのときに購入していて、結婚するときにそのまま持ってきました。その後、私も自分の本や資料を整理するために追加で購入しました。家に二人分の本が合流したことで、収納の見直しが必要になったんです。
──引っ越しの際、以前お使いになっていた場所と新しい場所では、天井の高さや梁の有無によって、そのままでは設置できない場合があります。当社では、そのようなお客様には新しい設置スペースのサイズに合わせて本棚を加工することも多いのですが…。
うちはたまたまサイズがギリギリ合ったのでお願いせずにそのまま設置できました。大掛かりな調整も必要なく、前の家からスムーズに移せたのは助かりました。
──長く使っていただけて嬉しいです。特に気に入っている点があればそれも教えてください
収納力はもちろんですが、壁がなくても自立して美しく収まるデザインが気に入っています。うちでは間仕切りとして両面から使える場所もあり、そういう本棚はなかなかありません。高さを選べる点も魅力で、文庫本と単行本をどう並べるかは本好きにとって永遠の課題です。さらに、背面に奥行きのある収納スペースがあるのも画期的だと思います。見た目の美しさと収納力の両立は、毎日の暮らしの満足度に直結します。

本棚は知識の拡張
──三宅さんにとって、本棚のある暮らしとは。具体的な経緯を教えてください。
大学時代の恩師が「本の内容を忘れても、その本がどこにあるか分かれば、それは脳の外に知識が拡張されている状態だ」と話してくれました。その言葉は今も強く心に残っています。本棚が整っていると、自分の頭の中まで整理されている感覚になるんです。反対に、本棚が散らかっていると気持ちも落ち着きません。本棚は、私にとって知識の地図であり、自分の思考の外付けハードディスクのような存在です。

読書習慣と積読
──読書はいつ頃から習慣になったのですか?
小さい頃からです。本や漫画を読むのが大好きで、外で遊ぶより家で本を読んでいました。特に小学校高学年から中高生にかけては、図書室や書店が自分の居場所でした。家にあった本棚の存在も大きく、自然と本と一緒に過ごす時間が増えていきました。
──積読はありますか?
もちろんあります。まだ読んでいない本も、自分だけの図書館のようなものです。興味があるテーマの本が揃っている状態は、とても贅沢だと思います。ページを開くタイミングはそのときの自分次第。だからこそ積読は、可能性のストックでもあります。
──三宅さん、電子書籍は利用されますか?
はい、移動中やちょっとした空き時間にはとても便利です。ただ、電子だと購入したことを忘れてしまうことも多いですね。紙の本は視界に入ることで存在を覚えていられますし、「早く読みたい」という気持ちを持続させてくれます。なので、じっくり読みたい本や手元に置いておきたい本は紙で買うことが多いです。
古典との出会い
──三宅さんの専門は古典文学と理解しています。古典文学に興味を持ったきっかけを教えてください
中高時代に読んだ氷室冴子さんの平安時代を舞台にした小説シリーズがきっかけです。あとがきに古典の元ネタが紹介されていて、『源氏物語』などを手に取るようになりました。最初は受験勉強のつもりで読んでいたのですが、思いのほか面白く、大学では本格的に古典文学を学ぶことにしました。
──古語と現代語の違いに興味があるそうですね。
はい。例えば「優しい」は昔は「身が痩せ細るほど立派だ」という意味でしたし、「憧れる」は「彷徨い歩く」という意味でした。現代の「やばい」と古語の「いみじ」も、良くも悪くも程度の大きさを表す共通点があります。意味の変化をたどると、その時代の人々の感覚や価値観が見えてきて、とても面白いです。

千年前の言葉が今も生きている
──言葉は映像や画像と違って残ると感じますか?
そう思います。映像や写真は10年前のものでさえ古さを感じますが、千年前の文章を今も読めるのは本当にすごいことです。特別な保存環境がなくても残っているのは、言葉が持つシンプルさと柔軟さのおかげかもしれません。
──現代人が古典を読む意義は?
日々の課題から少し距離を置き、長い時間軸で物事を考えられるようになります。古典は、時代や文化の異なる価値観に触れさせてくれる存在です。忙しいビジネスパーソンこそ、古典を読むことで思考が広がり、視野を広く持てるようになると思います。

インタビューを終えて三宅香帆さんにとっての本棚とは、あらためて知識や記憶をしまうだけでなく、思考を広げるための「拡張装置」であると認識しました。そこに並ぶ本は、現代と古典を自由に行き来するための通路であり、日常に長い時間軸の視点をもたらす存在であると言えます。